AIの提案がいつも“正しい”とは限らない。
体調・気温・気持ち──数値化できない変数が増える日は、人間の直感が主役になる。
本稿では、AIが示すメニューを“あえて外す判断力”と、その実践方法をまとめる。

AIの提案が外れる日がある理由
- 入力データのズレ:睡眠不足・仕事のストレス・月経などが反映されにくい。
- 気象条件の変化:気温・湿度・風。走力は同じでも体感強度が大きく上がる。
- 感情の波:やる気が出ない/逆に昂ぶり過ぎる──いずれも怪我リスク増。
AIは過去データの平均から最適を出す。一方、ランはその日の一発勝負。ここにギャップが生まれる。
沈黙にどう向き合う?「判断の3段階」
- Plan(メニュー確認):AI提案メニューを把握。目的(VO₂max/閾値/回復)を言語化。
- Check(現状診断):主観RPE(6〜20)と朝の自覚症状を1分でチェック。
- Act(微調整実行):強度を±1段階調整 or ドリル・ジョグに切替。中止も正解と認める。
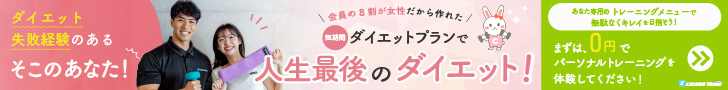
実践プロトコル:メニュー別の“外し方”
① インターバル(閾値〜VO₂max)
- 息が上がりすぎる→ レスト+15〜30秒追加 or 1本減らす
- 風が強い→ 追い風区間のみ質を確保、向かい風はフォーム意識に切替
② テンポ走(LT)
- 心拍が想定より+5以上→ ペース-5〜10秒/kmで“閾値感覚”を維持
- 脚が重い→ 20分→10分×2に分割し、可処分集中力を節約
③ ロング走
- 睡眠不足/暑熱→ 距離-20〜30%短縮+給水テストに目的変更
- 違和感あり→ 90分ウォークブレンド(10分走+1分歩)で循環だけ保つ
“手放す勇気”を仕組みにする
感情で判断すると後悔しやすい。だからルール化が効く。
- 朝の主観RPEが15(しんどい)以上なら強度メニュー中止
- 睡眠時間<6h+安静時心拍+6bpmで回復走へ
- 暑熱指数(WBGT)25以上でペース指示→時間指示に変更
AIは「ブレーキ」役に、あなたは「ハンドル」役に。役割分担ができたとき、走りは安定する。

🏁 まとめ:AIが沈黙する日は、直感を検証するチャンス。
「外し方」を決めておけば、迷いは最小、成果は最大になる。
\ AI×マラソン シリーズをもっと読む /
VOL.01
AIが見抜いた「限界のサイン」
データが示す“本当の疲労”とは何か。AIコーチの診断結果に迫る。
VOL.02
AIが描く「理想の練習リズム」
週単位で自動調整されるAIトレーニングの仕組みを解説。
VOL.03
AIが提案する「休む勇気」
リカバリー戦略を“勇気”として考える新しいマラソン理論。
VOL.04
AIコーチが導き出した「休む勇気」
データだけでは測れない、心のリカバリーをテーマに語る。
VOL.05
心拍では測れない走り
AIが導けない“人間の強さ”とは何か。心のデータに焦点を当てる。
VOL.06
AIが沈黙したとき
データが語らない「感情のブレ」こそ、成長のサインかもしれない。
VOL.07
AIが見た「限界の先にある心」
データが示さない“人間の強さ”をテーマに描く第7話。
VOL.08
AIと共に走る「沈黙の時間」
AIが黙ったとき、心は何を語るのか。静けさに宿る成長を描く。
🔁 野田商店の人気シリーズはこちら
この記事のつづきにどうぞ
「これって保険でどうなるの?」「他のケースも知りたい…」と思った方へ。野田商店の保険シリーズと、くらしに役立つ解説記事をまとめました。
🔥 火災保険シリーズ(代表記事)
🚗 自動車保険シリーズ(全20本予定)




コメント