家の壁に穴が空いたり、床に傷がついたりしたとき、まず頭に浮かぶのは「自分で直そう」という選択肢かもしれません。
最近はホームセンターやネット通販で材料も道具も簡単に手に入る時代。DIYで修繕すれば業者に依頼するより安く済むのは間違いありません。
しかしそこで気になるのが、「DIY修理にかかった費用は火災保険で補償されるのか?」という点です。
今回はDIYと火災保険の関係を深掘りし、領収書や申請の裏ワザ的な活用法を解説します。
火災保険はどこまでDIY費用をカバーする?
火災保険は火事だけでなく、台風や水漏れなどの「偶然の事故」による損害もカバーします。
基本的には「元の状態に戻すための修理費用」が対象ですが、ここでポイントになるのが修理方法と証明書類です。
– 業者修理の場合 → 見積書や領収書がはっきりしているため請求がスムーズ。
– DIY修理の場合 → 材料費は証明できても「修理の妥当性」が問われやすい。
そのため「DIY=一切補償されない」というわけではありませんが、業者修理と比べるとハードルが上がります。
DIY修理のメリットとデメリット
メリット
・修理費を大幅に節約できる
・好きなタイミングで作業できる
・修理スキルが身につく
デメリット
・保険申請で認められにくい
・修理精度が低いと再発のリスクがある
・写真や証拠がないと「損害の事実」を証明できない
つまりDIYはコスト面では魅力的ですが、保険申請と両立させるには証拠を残す工夫が欠かせません。
DIY費用を保険申請するためのポイント
保険申請を有利に進めるためには、次の3つを徹底することが大切です。
- 修繕前・途中・修繕後の写真を残す(被害の証拠と修復の過程を見せる)
- ホームセンターや通販の領収書を保管する
- 業者見積もりを併用する(DIYした場合でも「業者ならこの金額」という基準があると認められやすい)
実際に、壁紙の張替えや床の補修をDIYで行った人が「材料費の領収書+写真」で一部補償を受けられた事例もあります。
保険会社によって扱いは異なるため、まずは代理店に相談するのが賢明です。
DIY修理と業者修理を組み合わせる“裏ワザ”
実はDIYと業者修理をうまく組み合わせることで、保険をより活用しやすくなります。
例えば…
- 大きな破損部分は業者に依頼し、その領収書を保険申請に活用する
- 小規模な部分(細かい補修や仕上げ)はDIYで行い、自己負担を減らす
このように役割分担をすれば「保険申請の安心感」と「DIYによる節約」を両立できます。
特に台風や地震後の被害では、広範囲の修繕をすべてDIYで行うのは大変なので、この方法はおすすめです。
実際にあったケース
・壁に穴が空いた → 業者の見積もりでは修理費10万円。DIYでは2万円で済んだ。
→ 領収書と写真を提出し、差額は減額されたが一部補償を受けられた。
・床の傷 → DIYで補修し、材料費の領収書を提出。
→ 補償対象外となったが、写真を残していたため次回の被害申請時に参考資料として活用できた。
このようにケースバイケースですが、「証拠を残す」ことが共通のカギになります。
まとめ:DIY好きなら“保険+証拠”をセットで考えよう
火災保険は本来、業者修理を前提とした仕組みですが、DIY修理でも材料費や一部費用が認められる可能性があります。
ポイントは以下の3つです。
- 必ず写真を残す
- 必ず領収書を保管する
- 可能なら業者見積もりも併用する
「壊れたらすぐDIY」ではなく「まず証拠を残してからDIY」。
この順番を守るだけで、DIYと保険を賢く組み合わせることができます。
保険を味方につければ、DIYがもっと安心で楽しいものになりますよ。

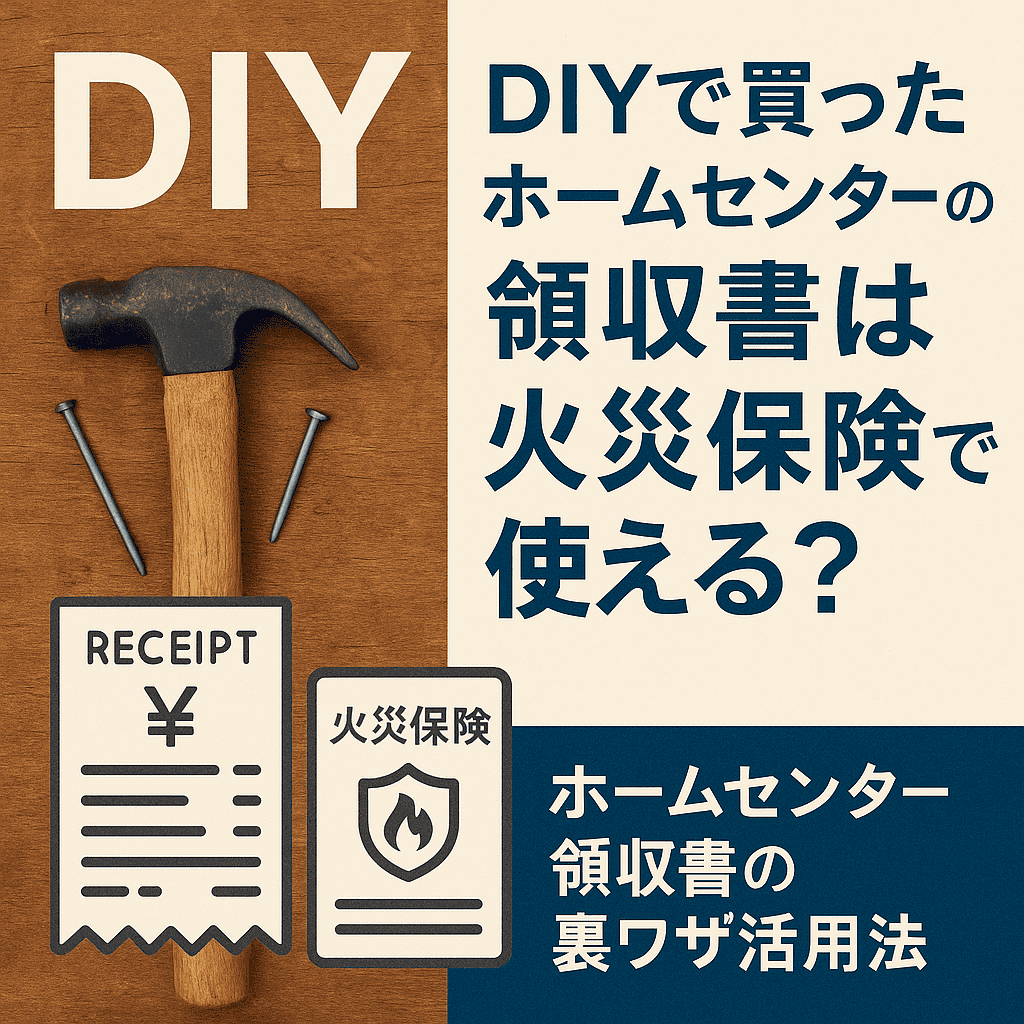


コメント